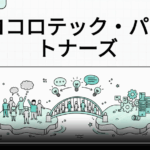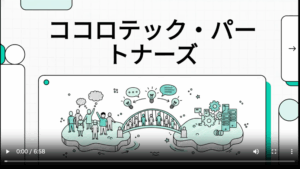私たちは、なぜ行動するのでしょうか?
「やらなければならないから」と感じることもあれば、「やりたい!」と自発的に取り組むこともあります。このように、行動の動機には質の違いがあります。この違いを説明するのが、心理学者エドワード・デシとリチャード・ライアンによって提唱された「自己決定理論(Self-Determination Theory, SDT)」です。
この記事では、自己決定理論の基本的な考え方、その応用例、そして私たちの日常生活にどう役立つのかを解説します。
自己決定理論とは?
自己決定理論は、人がなぜ行動を起こすのか、その動機の質に注目する心理学の理論です。この理論は、「やらされている」という外的な動機(コントロールされた動機)と、「やりたい」という内的な動機(自発的な動機)が人のパフォーマンスや幸福感に与える影響を探ります。
動機の2つのタイプ
- 外発的動機
外から与えられる報酬や罰に基づく動機です。- 例: 良い成績を取るために勉強する、上司に褒められるために頑張る。
- 例: 良い成績を取るために勉強する、上司に褒められるために頑張る。
- 内発的動機
行動そのものが楽しい、興味深い、または満足感をもたらすための動機です。- 例: 新しい知識を学ぶのが楽しいから勉強する、自分の趣味に没頭する。
自己決定理論の3つの基本的欲求
デシとライアンは、人が自発的に行動し、成長するためには、以下の3つの基本的欲求が満たされる必要があると述べています。
1. 自律性(Autonomy)
自分で選び、コントロールできていると感じること。
- 例: 学校や職場で、自分のやり方でタスクを進められる環境。
2. 有能感(Competence)
自分が物事をうまくやれる、自信が持てると感じること。
- 例: チャレンジングだけど達成可能な目標があること。
3. 関係性(Relatedness)
他者とつながり、受け入れられていると感じること。
- 例: チームで協力し、達成感を共有する経験。
これらの欲求が満たされると、私たちは内発的動機が高まり、幸福感や自己成長が促進されます。
自己決定理論の実生活での応用
自己決定理論は、教育、職場、健康、スポーツなど、さまざまな分野で応用されています。以下はその具体例です。
1. 教育現場
教師が生徒の自律性や有能感をサポートすると、生徒の学習意欲が向上します。
- 実践例: 強制的な宿題ではなく、選択肢を与えることで生徒の自律性を尊重する。
2. 職場での応用
社員が自律的に働ける環境を提供することで、モチベーションとパフォーマンスが向上します。
- 実践例: プロジェクトの進め方やスケジュールを自分で決められる裁量を与える。
3. 健康行動の促進
運動や健康的な食事を「やらされている」と感じるのではなく、「自分のために選んでいる」と思うことで、習慣化しやすくなります。
- 実践例: フィットネスプランを自分の好みに合わせて選択する。
4. 子育て
子どもが自分で選択する機会を増やし、成功体験を積むことで、内発的動機が育まれます。
- 実践例: 習い事や課題を選ぶ際、子どもの意見を尊重する。
自己決定理論を日常生活に活かす方法
自己決定理論を意識することで、自分自身や他者との関係性をより良いものにすることができます。
1. 自分の動機を振り返る
- 今取り組んでいることは「やらされている」と感じているのか、「やりたい」と感じているのかを考えましょう。
- もし外発的動機に頼りすぎている場合、その活動の中に楽しさや意味を見つけられる方法を探してみてください。
2. 環境を整える
- 自分で選択肢を持てる場面を増やす。
- 達成可能な小さな目標を設定し、成功体験を積む。
3. 他者をサポートする
- 周りの人が自律性を感じられるように配慮する。
- 相手の努力や進歩を認め、有能感を高める言葉をかける。
動機を知ることで、より豊かな人生を
自己決定理論は、なぜ私たちが行動するのか、そしてその動機の質が幸福感やパフォーマンスにどのように影響するのかを教えてくれます。外的な報酬に依存するのではなく、内的な動機を大切にすることで、より充実した人生を送ることができるでしょう。
投稿者プロフィール

-
人生理念は「やさしい世界をつくる」
しあわせ組織クリエイターとして、人のしあわせを実現するお手伝いをしています。
保有資格:国家資格キャリアコンサルタント、メンタルヘルスカウンセラー、ITコーディネーター、情報セキュリティスペシャリストなど
最新の投稿
 ブログ2025年11月11日優秀な若手が辞めていく理由──「退屈」という言葉の裏にある本音
ブログ2025年11月11日優秀な若手が辞めていく理由──「退屈」という言葉の裏にある本音 ブログ2025年11月7日URLを入れるだけで会社紹介動画ができる!
ブログ2025年11月7日URLを入れるだけで会社紹介動画ができる! ブログ2025年11月6日ブリーフセラピー「問題を見つけるより、変化を起こす」
ブログ2025年11月6日ブリーフセラピー「問題を見つけるより、変化を起こす」 ブログ2025年11月4日ChatGPTに社内情報を学習させていませんか?
ブログ2025年11月4日ChatGPTに社内情報を学習させていませんか?